更新日:
変形性膝関節症とは
変形性膝関節症とは、膝の関節が加齢や過度の負荷によってすり減り、痛みや動きの制限を引き起こす疾患です。
主に中高年に見られ、関節内の炎症や関節組織の変性が関与し、末期には骨の変形も引き起こします。
症状
変形性膝関節症の主な症状は大きく2つ。ひざの痛みと変形です。
また、疾患が進行するにつれてひざの可動域(動かせる範囲)が徐々に制限されるようになり、末期には日常生活に大きな支障をきたすようになります。
具体的には、正座やしゃがむ動作、階段の上り下りがつらくなったり(特に下りで痛みを感じる)、動き始めにひざの後ろが痛い、素早く動けない、歩行時にふらつくなどの症状がみられます。
-
- 初期に見られる症状
-
- 起き上がるとき、動き出すときにひざがこわばる(重く感じる/鈍い痛みを感じる)
- 正座、階段の上り下り、急な方向転換といった動作時に痛みを感じる
-
- 中期に見られる症状
-
- ひざの痛みがいつまでも続く
- 正座、深くしゃがむ動作、階段の上り下りなどが困難
- ひざが腫れ、熱感を持つ
- 歩くときしむような音がする
- ひざに水がたまる
-
- 末期に見られる症状
-
- これまでに見られた症状がさらに悪化
- 歩く、座る、しゃがむといった日常的な動作が困難になる
- 痛みに苛まれる時間が長くなり、精神的負担が大きくなる
痛みの原因
痛みの原因は、ひざの関節内にある「滑膜(かつまく)」の炎症です[1]。
関節の中は関節液という液体で満たされていますが、炎症は関節液の中を漂う「軟骨のかけら」が関節の内側を覆う滑膜を刺激することで、炎症が生じます。
軟骨の表面は本来非常に滑らかで、こすっても簡単にはすり減りません。しかし、ひざは1日に何千回もこすれます。これが数十年続くと、タイヤがすり減りるように徐々に磨耗が進んでいきます。その結果、すべすべしていた軟骨の表面はザラザラと毛羽立ちはじめ、軟骨自体が削り取られていくのです。こうして削り取られた軟骨のかけらが滑膜を刺激して、炎症を引き起こします。

変形の原因
ひざの変形は、軟骨がすり減った結果、骨どうしがぶつかり合うことで生じます。
軟骨がすり減って消失してしまうと、大腿骨(だいたいこつ:ももの骨)と脛骨(けいこつ:すねのの骨)が直にぶつかり、互いの骨をすり減らしてしまいます。
骨には再生能力があるため、すり減って失われた骨を再生させようとします。しかし、ひざには常に体重がかかっているため、正しい位置に骨を再生させることができず、横にはみ出した状態で増殖してしまいます。
このはみ出して増殖した骨を骨棘(こっきょく)と呼びます。
骨棘の形成が進むと、O脚やX脚のひざの変形も進行します[2]。
こうなると、ちょっとした動作でも激しい痛みを伴うようになり、やがてはひざを動かさなくても痛みを感じるようになります。
このような状態になると、手術を検討しなければなりません。

どんな人がなりやすいか?
変形性膝関節症は、加齢によって発症することが多く、50代以降から急増します[3]。また、比較的に男性より女性に多い疾患とも言われています。女性に多い理由ははっきりわかっていませんが、男性に比べて関節が小さいこと、筋肉が少ないこと、ハイヒールをはくこと、閉経後に女性ホルモンが減少することなどが影響していると考えられています。
この他にもひざに負担がかかる状態である、肥満や筋力の低下、スポーツ歴などが原因とされています。介護職など、日頃から膝を酷使する仕事についていると、性別問わず30代や40代でも発症することはあります。
<変形性膝関節症になりやすい人の特徴>
- 50代以降
- 女性
- 肥満
- 膝に負担のかかる仕事のに従事している(農業、漁業労働)
- ひざを酷使するスポーツ(スキー、サッカーなど)の経験者
- リウマチ、骨壊死などの既往がある人
変形性膝関節症の治療の進め方
変形性膝関節症の診断と治療方針は、問診、触診、検査を経て決定されます。
問診・触診
問診では、医師が症状について細かく質問します。
具体的には、痛みを感じ始めたのはいつ頃かひざのどこが痛むか1日のうち常に痛いと感じているのか、痛くない時間もあるのか日常のどんなシーンでどんな痛みを感じるかといった質問です。あらかじめ要点をまとめておくとスムーズに進みます。
また、ひざの周辺を指で押して、骨や腱、筋肉の状態を確認する触診も行います。
<問診で伝えるポイント>
| 医師の質問 | 伝え方の ポイント |
伝え方の例 |
| どこが痛みますか? | 場所を細かく伝える |
|
| どのような時に痛みますか? | 場面や状況を詳しく伝える |
|
| どのような痛みですか? 痛み以外の違和感はありますか? |
感覚を直感的/具体的に伝える |
|
その他にも、下記に該当するものがあれば、医師に伝えましょう。
・過去に骨折や脱臼などのけがをした経験がある
・家族に変形性膝関節症など関節の疾患がある
・激しいスポーツの経験/重労働に従事した経験がある
検査
ひざの内部や骨の状態を確認するため、レントゲン(X線)検査やMRI検査といった画像診断が行われます。この他に、膝痛の原因疾患を特定するために、膝関節の中にある関節液という液体を抽出して内容物を確認する関節液検査を実施することもありますが、必ずしも全ての検査を行うわけではありません。必要に応じて医師が判断します。
<ひざ痛の原因探索に行う主な検査>
| レントゲン検査 | MRI検査 | 検体検査 (関節液・血液) |
|
| どんな検査? | X線でひざを撮影し、骨の形状(変形や角度)を写真で確認します。 | 電磁波でひざを撮影し、関節内の組織の状態を画像で確認します。 | 関節液を注射器で吸い取り、粘り気や色味、成分から何の疾患か調べます。 |
| 何がわかる? | 骨の形から変形性ひざ関節症の場合は進行度がわかるので、それに応じた治療法を考えることができます。 | 軟骨や半月板や骨内の状態もわかるため、異常の発見及び、変形性ひざ関節症のリスク予測が可能です。 | 変形性ひざ関節症、関節リウマチや偽痛風、感染症など、関節炎が生じる疾患を鑑別することができます。 |
| 必要なケースは? | 診察で骨に関する異常が疑われる場合に行います。 | レントゲンで異常が確認できなかったり、治療方針を考えるためにより詳細な情報が必要な場合に行います。 | ひざが腫れたり水がたまったりしていて、変形性膝関節症以外の疾患の影響が考えられる場合に行います。 |
▷MRI検査について
当院ではMRI検査と整形外科専門医による再生医療の適応診断を組み合わせた「MRIひざ即日診断」を行なっています。当院の治療で改善が期待できるか、気になる方はぜひご相談ください。
治療方法
診察や検査で判別した重症度に応じて治療を開始します。
治療方法は「保存療法」と「手術療法」に分けられます。
初期は進行を遅らせる目的の保存療法がメインですが、末期に向かうにつれて手術療法にシフトしていきます。
近年、比較的重度の方にも適応がある新たな治療選択肢として、再生医療も加わりました。

運動療法
重症度にかかわらず、全ての患者さんが対象となる治療法です。
ひざを支える筋肉を鍛えることで、痛みを軽減し、ひざへの負担を軽くすることができます。また、ストレッチで筋肉をほぐすことは、関節の可動域の維持と向上に役立ちます。
こうした運動療法によるひざの痛みや運動機能の改善の効果は、数々の研究で確認されており、変形性膝関節症の治療ガイドラインでも高く推奨されている治療法です[4][5][6][7][8][9][10][11]。
運動療法は変形性膝関節症治療の中心かつ基本であり、重症度にかかわらず常に継続すべきものと認識してください。

薬物療法
ひざの痛みが激しいとどうしても運動から遠ざかり、筋力の低下を引き起こします。すると、ますます運動が億劫になって、さらに筋力が衰えていく可能性があります。
薬物療法の大きな目的の一つは、この悪循環を断つことです(ひざの痛みを抑えることで、運動療法を続けるモチベーションを維持します)。

ヒアルロン酸注射
ひざ関節の中は関節液という液体で満たされています。
この関節液に近いヒアルロン酸をひざの中に注入することで、関節の滑りを滑らかにするとともに、痛みを緩和します。
薬物療法と併用されることが多い、最も一般的な保存療法の一つです。▷治療の詳細は診療内容の「ヒアルロン酸注射」をご覧ください。

寒冷/温熱療法
患部を温める治療を温熱療法、冷やす治療を寒冷療法と言います。
温熱療法では血行促進と可動域の拡大を狙います。温湿布やホットパック、入浴などの他に、医療機関で受ける電気療法、レーザー療法、超音波治療などがあります。
寒冷療法は患部の炎症が強いとき、腫れを抑えるのに有効です(ただし、冷やしすぎは要注意です)。

再生医療
再生医療は、血液や脂肪細胞など自分自身の組織を材料とし、これをひざ関節の治療に活用します。現在実用化されている主な治療法は、PRP療法と培養幹細胞治療です。
PRP療法は、患者さんの血液から多血小板血漿(=PRP)という成分を抽出し、患部に注入します。血小板から分泌される成長因子が組織の修復を促進すると考えられています。
当院ではPRPに含まれる成長因子を濃縮したPRP-FDを使用しています。
培養幹細胞治療では、脂肪に含まれる幹細胞を抽出し、これを培養して患部に注入します。多数の幹細胞の働きで、組織の修復や痛みの抑制が期待できます。[12][13]
自己組織を使用するので、いずれも拒否反応の心配はありません。保存療法(薬物療法やヒアルロン酸注射)を行っても効果を実感できないという人、医者に手術を勧められていて受けるべきか迷っている人などは検討の価値があります。
実際、痛みや関節機能の改善という面で、薬物療法を上回る利益がもたらされたという研究も報告されています[14][15]。

-
再生医療で治療してみたい方
-
再生医療の適応があるか知りたい方
手術療法
保存療法で十分な効果が得られない場合に、手術療法を検討します。
高位脛骨骨切り術は、骨を切ってつないでO脚を矯正する手術です。以前は若年者によく行われていましたが、人工関節の耐用年数が伸びた現在では、実施件数が減りつつあります。
人工関節置換術は、関節を切り取って人工関節に置き換える手術です。利点は、術後は痛みをほとんど感じなくなることですが、正座のように深くひざを曲げる動作はできなくなります。
この他に、関節鏡視下手術があります。体への負担が少ないので、高齢者や持病のために大きな手術を望まない人、人工関節置換手術を先延ばしにしたい人などに行います。▷手術療法の詳細はコラム「変形性膝関節症の手術【費用/タイミング/術後の生活について】」をご覧ください。

変形性膝関節症の予防方法
変形性膝関節症を予防するために最も重要なことは、関節に負担をかけないことです。そのために日々の生活で注意していただきたいこと、習慣的に行っていただきたい運動についてご紹介します。
膝に負担をかけない動作を心がける
<生活様式全般>
できるだけ寝るときはベッド、座る際は椅子を、お手洗いも洋式を利用してください。要は生活様式全般を和式から洋式変えていただくのが望ましいということです。
住宅事情等で難しい場合は、座椅子を使用したり、便器に洋式の便座をかぶせるなどして対応していただければと思います。
<立ち方>
O脚の方は足の向きが内向きになりがちで、そのせいで膝の内側が消耗しやすくなっています。よって爪先を開いて立ち、内側にかかる負荷を分散させるように心がけてください。その際、足の親指に重心が乗るように意識します。
一方、X脚の方は両足を平行に揃えて、足の小指に重心を乗せるような意識で立っていただくと良いでしょう[16]。
| O脚の場合の立ち方 | X脚の場合の立ち方 |
| つま先をやや広げる足の親指に重心を乗せる | 左右の足は平行に置く足の小指に重心を乗せる |
<座り方>
床に直接座る生活をしないのが理想ですが、難しい場合は次の点を意識してください。
- 正座用の座椅子を利用する
- 膝が痛む場合は、痛む方の足を立てて片膝の姿勢をとる
- 立ったり座ったりするときは、テーブルを掴むなどして腕の力も利用する
- 掴むものがなければ、周囲の人の力を借りる
<階段の上り下り>
膝に負担をかけないように、以下の点を心がけてください。
- 手すりに捕まる
- 重心をやや前の方に置く
- 一段一段、同じ段に両足を乗せてから次の段に進む
<歩行>
膝の痛みが治まってきたら積極的に歩くようにしてください。
適度な歩行は望ましいのですが、あまり長距離歩くのは控えてください。痛みを感じるようでしたら無理をせず中止してください。
<趣味>
登山とランニングはお勧めしません。いずれも中高年世代の方の間で人気ですが、膝の痛みを抱えている方はなるべく控えてください。
週に2回程度、各回20分ぐらいのウォーキングから始めてみてください。
<入浴>
湯船に浸かることでこわばった筋肉が柔らかくなるので、痛みの改善が期待できます。シャワー浴などで済ませず、なるべく湯船に浸かってください。立ったり座ったりに不安がある方は、浴室に手すりなどを設けるのも手です。
適正体重を目指し、少しでも減量する
肥満や過体重は、膝関節の悪化を加速させる大きな要因の一つです。心がけていただきたいのは2点。バランスの良い食生活と、有酸素運動の継続です。
たった3kg体重を落とすだけで、歩行時に膝にかかる負担は9kg、階段の上り下りだと20kg程度軽減することができます。少し太り気味だという方は、わずかでもいいので減量を試みてください。
膝周辺の筋トレやストレッチを行う
痛いからといってあまり膝を動かさないと、膝の周辺の筋肉が衰えてかえって不安定感が増してしまいます。当院では、膝の筋力維持・強化に有効な筋トレやストレッチ動画を数多くご紹介しておりますので是非お役立てください。
ここでは、膝関節の保護に特に大きな役割を果たす太もも(大腿四頭筋)の筋トレとストレッチを中心ご紹介します。
<関節の動きを滑らかにする「膝の曲げ伸ばし運動」>
運動のウォーミングアップに最適な筋トレです。ウォーキングなどの前に行うことをおすすめします。
①椅子に深く腰かけ、姿勢を正します。
②2秒かけて膝を伸ばし、また2秒かけて曲げるという動きを、片足ずつ行います。
③準備体操なら20回を2セットずつが適当です。

<膝への負担を軽減する「タオルつぶし運動」>
大腿四頭筋は太ももの前側の筋肉です。膝に加わる衝撃を吸収する役目を担うこの筋肉を鍛えることで、膝への負担軽減が期待できます。
①バスタオルを1枚用意し、コンパクトに丸めます。
②そのタオルを、伸ばした足の下に置きます。膝が伸び切る人は膝のお皿より太もも側に、伸び切らない人はふくらはぎ側に調整ください。
③つま先を天井に向け、タオルをつぶすイメージで膝が伸びるよう、太もも前側に力を入れます。そして5秒キープ。
④これを10回3セット行います。

<寝る前に行ってほしい「太もものストレッチ」>
筋トレや有酸素運動の前後は、筋肉をほぐしてケガを予防するために、ストレッチを行いましょう。ここでは、膝痛予防に最も有効な太もも(大腿四頭筋)のストレッチをご紹介します。
①バスタオルを腰の下に敷きます。
②右足の甲を右手で掴みます(余裕のある人は、踵をお尻に近づけていきます)
③太ももの前側が伸びるのを感じたところで20〜40秒キープします。
④反対側の足も同様に行います。

変形性膝関節症のよくある質問
-
変形性膝関節症は治療したら治りますか?
完治は難しいですが、痛みを緩和させることは可能です。
残念ながら、軟骨を元通りにして完治させる方法は確立されていません。ただ、治療することで痛みを緩和、もしくは解消させたり、軟骨がすり減っていくスピードを遅らせる効果が期待できます。変形性膝関節症の治療では、この“いかに進行させないか”という点が重要なポイントとなります。
治療を始める際には、まず膝の状態を正確に把握することが大事です。そうすることで治療がスムーズになり、早期回復も期待できます。
そのため当院では、患者様全員にMRI検査を受けていただくようお勧めしています。これによって、触診では気づきにくい水腫や、骨以外の関節組織全体の状態を把握できます。
▷検査のお申し込みは「MRIひざ即日診断」よりお願い致します。
-
変形性膝関節症を予防する手立てはありますか?
適度な運動で筋力を付け、ひざへの負担を減らすことが大切です。
有効とされているのが、適度な運動です。筋力を維持することでひざへの負担を軽減できますし、減量にもつながります。
激しいスポーツよりもウォーキングや自転車、水泳などのひざへの負荷が少ないものがおすすめです。すでに痛みを感じている方は無理をせず、ひざ関節への影響力の大きい大腿四頭筋(太もも前側の筋肉)にフォーカスしてトレーニングすると良いでしょう。またウォーキングなど、膝に負担の少ない有酸素運動を取り入れて、減量を試みるのもお勧めです。
▷具体的な運動療法の内容についてはコラム「【動画有り】変形性膝関節症に効く! 室内で簡単にできる筋力トレーニング」で詳しくご説明しています。
-
自分で治すことはできるのでしょうか?
自然治癒は望めません。医療機関で治療を受けてください。
変形性膝関節症は、軟骨のすり減りに端を発する疾患です。一度すり減った軟骨は放置しても元どおりになりません。膝は日常生活で必ず使いますので、放置すればすり減り度合いは進行し、症状悪化する一方です。膝の痛みが全て変形性膝関節症に起因するとは限りませんが、もし痛みを感じるなら、まずは整形外科を受診してください。早期に治療を開始すれば、それだけ予後も良好になる可能性が高くなります。
-
症状を悪化させないために日頃自分でできること、またはしてはいけないことはありますか?
以下の6点を普段から意識できると望ましいです。
①体重のコントロール毎日定期的に運動することと、栄養バランスを考えた食事の意識が基本です。BMI値22前後を目指し、体重コントロールを行いましょう。②生活習慣病の予防と治療糖尿病、脂質異常症、高血圧がある場合は、必要に応じて治療しましょう。血流や軟骨代謝が悪くなり、ひざ関節の状態が悪化する可能性があります。③継続的な運動(ただしひざへの負担が少ないもの)ももの筋力トレーニングや、ウォーキングをしましょう。運動するときは転倒して骨折しないよう、安全な場所で行いましょう。ウォーキングもアスファルトでなく、公園や運動場などの土の上で行うのがひざにとっては望ましいです。④サポーターや温熱用品で温める冷えるとひざの痛みが出やすくなります。市販されているサポーターや温熱用品で温めて、血行促進しましょう。温めるときは適度に保温し、低温やけどには注意しましょう。⑤ひざへの衝撃が少ない靴を使用する靴の中敷きでクッション性を高め、ひざへの衝撃を減らします。また荷重のバランスを調整し、ひざ軟骨へのストレスを軽減することで進行を抑えます。適切な靴を履くことは歩行状態を安定させ、転倒リスクの軽減にもつながります。⑥ひざに負担のかかる動作は避ける日常生活にもひざに負担のかかる動作はいろいろあります。重いものを持つこともそうですが、正座や和式トイレにも言えます。椅子や洋式トイレを利用する頻度を増やすことも対策のひとつです。
-
変形性膝関節症で用いるサポーターや装具について教えてください
主なものとしては、足底板、サポーター、杖があります。いずれも医師の指導のもと、ご自分に合ったものを使用してください。
足底板は、足の外側に楔形の板を差し込んで持ち上げる器具です。これによって、ひざをまっすぐに矯正し、関節にかかる負荷を均一にします。靴にいれるだけなので、簡易に使用できるというメリットがあります。
サポーターはひざを安定させるのに効果的です。ひざの筋肉が不足して不安定な人は歩きやすくなります。ただし、炎症が強いとサポーターをつけることで痛みが増すことがあるので注意してください。
その他、ひざへの負担軽減や転倒防止の目的で杖を使用することもあります。
参考
- [1] ∧黒澤尚(2020)『ひざ痛 変形性膝関節症 ひざの名医15人が教える最高の治し方大全』文響社.
- [2] ∧杉山肇ほか(2012)『名医が語る最新・最良の治療 変形性関節症(股関節・膝関節)』法研.
- [3] ∧Yoshimura, N., Muraki, S., Oka, H., Mabuchi, A., En-Yo, Y., Yoshida, M., ... & Akune, T. (2009). Prevalence of knee osteoarthritis, lumbar spondylosis, and osteoporosis in Japanese men and women: the research on osteoarthritis/osteoporosis against disability study. Journal of bone and mineral metabolism, 27, 620-628.
- [4] ∧黒田栄史(2009)『変形性膝関節症 正しい治療がわかる本』法研.
- [5] ∧Ettinger, W. H., Burns, R., Messier, S. P., Applegate, W., Rejeski, W. J., Morgan, T., ... & Craven, T. (1997). A randomized trial comparing aerobic exercise and resistance exercise with a health education program in older adults with knee osteoarthritis: the Fitness Arthritis and Seniors Trial (FAST). Jama, 277(1), 25-31.
- [6] ∧Petrella, R. J., & Bartha, C. (2000). Home based exercise therapy for older patients with knee osteoarthritis: a randomized clinical trial. The Journal of Rheumatology, 27(9), 2215-2221.
- [7] ∧O’Reilly, S. C., Muir, K. R., & Doherty, M. (1999). Effectiveness of home exercise on pain and disability from osteoarthritis of the knee: a randomised controlled trial. Annals of the rheumatic diseases, 58(1), 15-19.
- [8] ∧Kovar, P. A., Allegrante, J. P., MacKenzie, C. R., Peterson, M. G., Gutin, B., & Charlson, M. E. (1992). Supervised fitness walking in patients with osteoarthritis of the knee: a randomized, controlled trial. Annals of internal medicine, 116(7), 529-534.
- [9] ∧Hinman, R. S., Heywood, S. E., & Day, A. R. (2007). Aquatic physical therapy for hip and knee osteoarthritis: results of a single-blind randomized controlled trial. Physical therapy, 87(1), 32-43.
- [10] ∧Mangione, K. K., McCully, K., Gloviak, A., Lefebvre, I., Hofmann, M., & Craik, R. (1999). The effects of high-intensity and low-intensity cycle ergometry in older adults with knee osteoarthritis. Journals of Gerontology Series A: Biomedical Sciences and Medical Sciences, 54(4), M184-M190.
- [11] ∧川口浩. (2016). 変形性関節症治療の国内外のガイドライン. 日本関節病学会誌, 35(1), 1-9.
- [12] ∧Kim, K. I., Kim, M. S., & Kim, J. H. (2023). Intra-articular injection of autologous adipose-derived stem cells or stromal vascular fractions: are they effective for patients with knee osteoarthritis? A systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. The American Journal of Sports Medicine, 51(3), 837-848.
- [13] ∧Issa, M. R., Naja, A. S., Bouji, N. Z., & Sagherian, B. H. (2022). The role of adipose-derived mesenchymal stem cells in knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Therapeutic Advances in Musculoskeletal Disease, 14, 1759720X221146005.
- [14] ∧Dai, W. L., Zhou, A. G., Zhang, H., & Zhang, J. (2017). Efficacy of platelet-rich plasma in the treatment of knee osteoarthritis: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arthroscopy: The Journal of Arthroscopic & Related Surgery, 33(3), 659-670.
- [15] ∧Shen, L., Yuan, T., Chen, S., Xie, X., & Zhang, C. (2017). The temporal effect of platelet-rich plasma on pain and physical function in the treatment of knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Journal of orthopaedic surgery and research, 12, 1-12.
- [16] ∧八木貴史(2017)『変形性ひざ関節症』主婦の友社.
監修医師
蓬田 翔太 医師(東京ひざ関節症クリニック銀座院 院長)

経歴
-
- 2012年
- 福島県立医科大学 医学部 卒業
-
- 2012年
- 脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院
-
- 2014年
- 福島県立医科大学 整形外科
-
- 2015年
- 飯塚病院附属有隣病院 整形外科
-
- 2015年
- 福島県立医科大学 大学院 医学研究科 修了
-
- 2016年
- 松村総合病院 整形外科
-
- 2017年
- 脳神経疾患研究所附属 南東北福島病院 整形外科
-
- 2018年
- 脳神経疾患研究所附属 総合南東北病院
-
- 2019年
- JA福島厚生連 坂下厚生総合病院 整形外科
-
- 2020年
- 総合南東北病院 整形外科
-
- 2023年
- 東京ひざ関節症クリニック 銀座院 院長
資格・免許
- 日本整形外科学会認定 専門医
- 日本整形外科学会認定 運動器リハビリテーション医
- 日本体育協会公認 スポーツドクター
所属学会
変形性膝関節症の記事一覧
-

高位脛骨骨切り術|後悔しないための基礎知識~方法・適応から再生医療との併用まで~
-

変形性膝関節症は予防できる? 【歩き方・筋トレ・食事】
-

人工膝関節置換術の注意点 【禁忌、メリット・デメリット】
-

膝を曲げた時の突然の痛み! 6つの原因と対処法 & ストレッチを解説
-

変形性膝関節症の手術の高齢者リスクを医師が分析|80代以上は要注意?
-
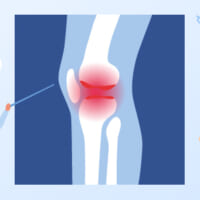
膝が腫れたらどうすべき? 考えられる病気と原因別対処法
-

膝が急に痛くなる原因は? よくある10の原因と解決法を医師が解説
-

【40代】歩いたときの急な膝痛!疑うべきは変形性膝関節症
-

変形性膝関節症の治し方を徹底解説!治療ごとのメリット・デメリットは?
-

変形性膝関節症の最新治療 ~再生医療で膝の痛みを改善









電話から

電話受付時間 9:00 〜18:00/土日・祝日もOK
ネットから






